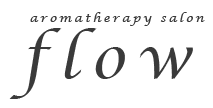茶道のお稽古を始めて、もうすぐ4年になります
今年の夏稽古はお茶室を飛び出して
先生とお稽古仲間と茅ケ崎市美術館へ

茅ケ崎にゆかりのある吉田耕三と北大路魯山人の
「うつわの彩」展を見てきました


器が引き立つ美しいしつらえ
私は裏千家のお作法でお茶を学んでいます
茶道の中の「表千家」「裏千家」などの「流派」
お稽古を始める前の私はそれを
「派閥」のようなものだと思っていました
でも実際にお茶の世界に触れて感じるのは
流派ごとに点前やお道具に違いがあっても
その根底にあるのはただ一つ
——「お客様をもてなし
一服のお茶を差し上げる」こと——
流派の違いがありつつも
それぞれが伝統を守りつつ、静かに共存している
そこに茶の湯の精神の根底に流れる
懐の深さを感じています
アロマセラピーの世界はどうでしょうか
メディカルアロマ、〇〇アロマ
イギリス式、フランス式・・・・
アロマの流派?が多様化する中で
その枠の間で新たな排他的思考が
生まれてはいないでしょうか
多様性の中で違いを尊重するはずが
小さな枠を作り、互いを排除する……
過去に私も公の場で
医療の中でアロマをやるのは医療者であるべき
ボランティアのアロマは所詮ボランティア
〇〇アロマが医療の中では正しい
そんな話に触れた経験があります
その時は、これまで自分が思いをもって届けてきた
アロマを否定された気がして
涙が出るほど悔しかったのですが
そのことは同時に、医療者でない自分は
アロマセラピーで何を届けられるのか?
アロマセラピーの本質とは?を
深く考えるきっかけになりました

アロマセラピーは
アロマセラピストのためにあるのではなく
クライアントのためにあります
そしてアロマセラピーの実践は
お茶が茶の湯の深い懐の中で実践されるように
自然、植物という深い懐の中で
その恵みを享受することへの感謝と謙虚さをもって
人のために役立てられるものであってほしい
そこに人間が作った「〇〇アロマ」のような
ステイタスはいらないと思っています
そして病院、介護施設、学校、サロン、イベント・・・
私がこの10年さまざまな場所で
アロマセラピーを届けてきて思うのは
患者さんやお客さまは、アロマセラピーに
イギリス式かフランス式か、メディカル・・・
ということをそもそも求めていません
学びの道筋や方式は
セラピストが経験や知識を積むための
土台になりますが
現場では方式の実践よりも
目の前の人が求めるアロマセラピーの
かたちを見つけ
それを安全に届ける、ということころにこそ
価値があります
方式や肩書き、資格
ラベル頼りのアロマセラピーでは
目の前の人を支えることはできません
病院、介護施設、学校、サロン、イベント・・・
場所・人が変わればアロマセラピーに
求められることも違うからです
私はどんな場所にいてもアロマセラピーを通して
「日々をより良く生きる」
そのお手伝いができればと思っています

11年前に始めたアロマ教室では
子育てで忙しいママがママではなく
自分としての時間を持ち
笑顔になれるアロマセラピーを
サロンを始めてからは日々の疲れを癒すことで
自分自身を取り戻したり
明日からまたがんばろう
と思えるアロマセラピーを
介護施設では、老いるということの中にある
不安や喪失に寄り添い
温かさを届けるアロマセラピーを
病院では、がん終末期
心と体の痛み、苦しみを少しでも癒し
心地よさや笑顔を感じていただける
アロマセラピーを

そして同じ病院の中にいる患者さんでも
楽しいアロマを必要とする方もいれば
苦しみを和らげてくれるアロマ
アロマはいらなくて、あたたかな手だけを
待ち望む患者さんなど、さまざまで
肩書や流派ではなく
どう届けるのか?にこそ
アロマの多様性があると思っています
それぞれの人、場所で
アロマセラピーの届け方はみな違いますが
たとえさまざまな困難や
命の期限を感じる日々の中にあったとしても
アロマセラピーは
「より良く生きる」ことの助けになる
という確信が私にはあります
その確信はこれまで
アロマセラピーを通して出会った
患者さんやお客さまから学ばせていただいたことで
私自身のアロマセラピーの支えになっています

アロマセラピストとしての確信や信頼は
肩書きや方式がくれるものでもなければ
競って得られるものでもありません
アロマセラピーで出会う目の前の人の
笑顔の積み重ねこそが
セラピストに学びと成長を与えてくれているのです
——目の前の人がどうしたら笑顔になれるか
どんな場所に居ても、どんなやり方でも
そこを大切に成長し続けるセラピストでありたいと
思っています

美術館の天窓から射す光 きれいでした